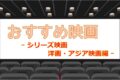日本にもしっかり根付いてきたハロウィン。毎年10月になるとハロウィンの飾り付けが目立つようになってきました。しかしハロウィン=仮装するお祭りと思っている人も少なくありませんね。そこでハロウィンのとは何なのか?ハロウィンの意味や起源、語源について少しおさらいしておきましょう。
スポンサーリンク
この記事の目次
ハロウィンとは
ハロウィンとは毎年10月31日に行われる伝統の民族行事で「ハロウィーン」とも言います。ハロウィンは元々11月1日に行われるキリスト教の「万聖節(全ての聖人と殉教者を記念する日)」の前夜祭で、秋の収穫を祝い、精霊や魔女を追い出し身を守るお祭りです。国によってハロウィンの時期は少し違いますが、正確には10月31日~11月2日がまでをハロウィンと呼んでいます。
ハロウィンの意味と起源
ハロウィンは、古代ケルト人(ヨーロッパの原住民)の風習がルーツとされています。古代ケルト人は10月31日を1年の終わり(日本でいうところの大晦日)と定め、この日に秋の収穫を祝い、魔物から身を守るために仮面を被ったり、魔よけの焚火を焚いたりしていました。
当時のケルト人の文化では、この日(31日)に亡くなった人の霊が家族の元に帰ってくると同時に、悪霊(魔物)もこの世にやってくると信じられていたので、人間も魔物の恰好(仮装)をして魔物に魂を取られないように身を守ったとされています。現在の仮装もココからきてるという訳です。
ハロウィンの語源は?
ハロウィンの語源は、「万聖節(諸聖人の日=Hallowmas)」の前夜を意味する「All Hallow's Eve(オール・ハロウズ・イブ)」が「ハロウィン(Halloween)」「ハロウィーン(Hallowe'en)」と短縮され訛って呼ばれるようになったそうです。
ハロウィンはキリスト教とは無関係?
先に、ハロウィンは、”キリスト教の「万聖節(全ての聖人と殉教者を記念する日)」の前夜祭”であり、「All Hallow's Eve(オール・ハロウズ・イブ)」から「Halloween(ハロウィン)」呼ばれるようになったと述べたので、ハロウィンがキリスト教のお祭りと勘違いしやすいのですが、実際にはハロウィンはキリスト教徒は無関係です。カトリック教会ではハロウィンは祝日ではなく、教会の宗教行事・公式行事として行われることはありません。
ジャック・オー・ランタン(Jack-o'-Lantern)とは

ジャック・オー・ランタン(Jack-o'-Lantern)は、カボチャをナイフで目、鼻、口にくりぬき、内側にろうそくを立てたもので、「かぼちゃのお化け」「かぼちゃのランタン」のことです。ハロウィンの象徴的なシンボルと言えます。
トリック・オア・トリート(Trick or Treat)とは

子供たちがハロウィンの日に各家庭を回りお菓子をもらう風習です。子供たちは「トリック・オア・トリート!(お菓子をくれないといたずらするぞ!)」と言いながら各家庭を回り、言われた方は「happy halloween!(ハッピー・ハロウィン)」と答えてお菓子をあげるのが習慣となっています。