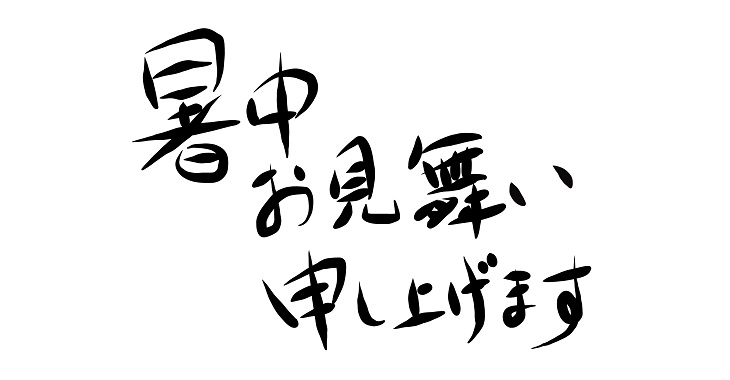クリスマスといえば赤い服に白いひげのサンタクロース。けれども最初から赤一色だったわけではありません。
宗教的な象徴、十九世紀の詩と挿絵、二十世紀の広告という三つの流れが重なって、いまの赤いサンタができあがりました。この記事では、その道のりをわかりやすく紹介します。
聖ニコラウスの伝説と「赤」のはじまり
サンタクロースの起源は、四世紀の小アジア(現在のトルコ)で活動したキリスト教の司祭、聖ニコラウスの伝説にあります。
困っている人々や子どもを密かに助けた慈善の行いが語り継がれ、やがて「贈り物を届ける聖人」として知られるようになりました。
聖ニコラウスが儀式で着ていた司祭服は赤だったとされ、その色は「愛」「情熱」「献身」を象徴します。この赤が、のちのサンタクロースの服のイメージにつながったと考えられています。
ただし当初のサンタ像は国や時代によって異なり、青や緑、茶色などの衣装も多く描かれていて、今のような赤いサンタが定着するのは、ずっと後の時代のことです。
十九世紀アメリカで整うサンタ像
十九世紀に入ると、アメリカでサンタの姿が次第に形づくられていきます。1822年、学者クレメント・C・ムーアが発表した詩「聖ニコラウスの訪問(A Visit from St. Nicholas)」では、トナカイのソリや白いひげ、ふくよかな体つきのサンタが登場。この詩が現代のサンタ像の基礎を築いたといわれています。
その後、1863年にアメリカの風刺画家トーマス・ナストが雑誌『ハーパーズ・ウィークリー』で赤っぽい衣装を着たサンタを描きました。ナストはその後も何度もサンタを描き、1890年には「クリスマス絵画集」を出版。これらの作品を通して、サンタのイメージはより人々の心に定着していきます。
広告が定着させた世界標準の「赤」
赤い服そのものは十九世紀から描かれていましたが、それを“世界共通のサンタ像”として広めたのは二十世紀の広告でした。
1931年、アメリカのコカ・コーラ社がホリデーキャンペーンで温かみのある人間的なサンタクロースを登場させます。

このサンタを描いたのは、スウェーデン系アメリカ人画家のハッドン・サンドブロム。赤い衣装に白いひげ、バラ色の頬で笑う陽気なサンタは人々の心をつかみ、その後30年以上にわたってコカ・コーラ社の広告に登場しました。
こうして、赤い服のサンタが世界中の共通イメージとして定着していきます。もともと宗教的な意味を持つ「赤」という色に、大衆メディアと広告の力が加わって広まっていきました。
日本に広まったサンタクロースの姿
日本では明治期にクリスマス行事とともにサンタが紹介されます。やがて児童雑誌や新聞が赤い帽子とコートの姿を描き、大正から昭和初期にかけて都市部を中心に浸透していきました。
海外のイメージを取り入れながらも、物語や装いに日本独自の工夫が見られるのが特徴です。昭和には「サンタは日本の子どものものに」という報道が出るほど、季節の風景として定着しました。
まとめ
赤は聖職の礼装に由来するとされ、慈愛と献身の象徴としてサンタ像に取り込まれました。十九世紀の詩と挿絵がサンタの姿を具体化し、赤い装いも広く知られるようになりました。
そして1931年のコカ・コーラ社の広告が、赤いサンタを世界共通のイメージとして定着させました。日本でも明治から昭和にかけて浸透し、今ではクリスマスの象徴としてすっかり馴染んでいます。
見慣れた赤いコートには、信仰と文化、そしてメディアの力が重なっています。この冬、街でサンタを見かけたら、その“赤”に込められた物語を少し思い出してみてください。