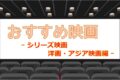夜空を見上げるとき、ふと心が静かになることはありませんか?
七夕(たなばた)は、そんな星を見上げる心に寄り添う日本の美しい年中行事です。短冊に願いを込め、笹に飾るこの風習は、古来より続く物語と信仰が融合した特別な日です。
今回は、七夕とは何か、どのように生まれ、どんな物語があるのかをご紹介します。
七夕とは?
七夕(たなばた)は、日本で毎年7月7日に行われる風情ある伝統行事です。
短冊に願いごとを書いて笹に結びつける風習は、今も学校や家庭、町のあちこちで見られ、夏の風物詩として人々に親しまれています。
この日には、夜空を流れる天の川をはさんで離れて暮らす織姫と彦星が年に一度だけ会うことを許されたという美しい伝説が語り継がれていますね。
余談ですが、私が小学生の頃に学校の行事だったと思いますが、クラスみんなで願いごとを書いたことがあります。私は「野球がうまくなりますように」と書いたのですが、「毎日カレーが食べたい」と書いていた友達がいて、みんなで大笑いしながら一時的に「キレンジャー」というあだ名がつけられたのを今でもよく覚えています。そのあだ名は浸透せず、2,3日で飽きて元の呼び名に戻りましたが。
七夕の由来は 古代中国と日本の文化が融合
七夕の起こりは、古代中国の「乞巧奠(きこうでん)」という風習にさかのぼります。
この行事は、機織りや裁縫の技術向上を願って、女性たちが星に祈りを捧げるというものでした。やがてこの風習は奈良時代に日本へ伝わり、日本固有の神事「棚機(たなばた)」と結びついていきます。
「棚機」とは、神様に捧げる神聖な布を織る女性(棚機女=たなばたつめ)によって行われていた儀式であり、その名残が“たなばた”という呼び名として現在も使われているのです。こうして、中国の星祭りと日本の古来信仰が融合し、今の七夕のかたちが生まれました。
七夕の物語 織姫と彦星の恋の伝説
七夕といえば織姫と彦星の物語が有名ですね。織姫は機織りの名手で、彦星は働き者の牛飼い。天帝(織姫の父)の許しを得て結婚しましたが、結婚後はお互いに夢中になり仕事を怠けてしまいます。
怒った天帝は二人を天の川の両岸に引き離し、年に一度、7月7日の夜にだけ会うことを許した…というのが七夕の伝説です。この物語は、中国の星座伝説「牽牛織女伝説」に基づいています。
七夕の風習 短冊と飾りに込められた願い
七夕の夜、人々は色とりどりの短冊に願いごとを書いて、笹の葉に飾ります。短冊のほかにも、紙で作る折り鶴や網飾り、星形の飾りなどさまざまな装飾があり、それぞれに意味があります。
笹は邪気を払うと信じられており、願いを天に届ける「媒介」として大切にされてきました。今では、勉強、健康、恋愛、家内安全などさまざまな願い事を書いて飾っていますね。今年のあなたの願い事は何でしょうね?
まとめ
七夕はただの「イベント」ではありません。天と地、過去と現在、人と人のつながりを思い出させてくれる静かで美しい行事です。日々の忙しさの中でも、一年に一度、空を見上げて願いごとをする時間は心を整えるきっかけになるかもしれません。
また日本各地では、七夕を祝う祭りが開催されます。特に有名な祭りとして、以下の日本三大七夕祭りがよく知られていますね。
・宮城県仙台市の「仙台七夕まつり」
・神奈川県平塚市の「湘南ひらつか七夕まつり」
・愛知県安城市の「安城七夕まつり」
また、京都や大阪などの神社・寺院でも、短冊奉納やライトアップイベントが行われ、幻想的な雰囲気を楽しめますよ。

「仙台七夕まつり」

「湘南ひらつか七夕まつり」

「安城七夕まつり」
今年の七夕は、少し立ち止まって自分自身の願いと向き合ってみるのもいいですね。