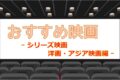毎年6下旬ごろにやってくる夏至。夏至を迎えると、本格的な夏の訪れが近づいてきたなと思う人も多いでしょう。この時期は自然も生き生きし始め、季節の変化を体感できるタイミングです。今回はそんな夏至について説明します。
夏至(げし)とは?
夏至(げし)は、1年の中で昼が一番長く、夜が一番短い日のことで、「1年で最も昼が長い日」とされています。
なぜ昼が長くなるの
地球は少し傾いた(約23.4度)まま太陽のまわりを1年かけて回って(公転)います。そのため、夏の時期には北半球(日本など)が太陽の方向に最も傾くため、太陽が高い位置を通り昼が長くなるんです。
2025年の夏至の日は?
2025年の夏至の日は6月21日(土)です。夏至の日の日の出から日の入りまでの日照時間は冬至よりも約5時間も長くなります。この時期は梅雨の最中ですが、「夏に至る」と書く通り、季節は確実に夏の本番へと向かい始めていきます。
夏至の風習は?
夏至に関しては全国的な行事や風習などはあまりありませんが、地域ごとに特有の風習や食文化が受け継がれている場所も存在します。以下に主なものをまとめてみました。
三重県
三重県で行われる「夏至祭」は有名です。伊勢市にある二見興玉神社で、夏至の日に夫婦岩の間から昇る朝日を浴びながら禊を行います

関西地方
関西地方の一部では、「稲がタコの吸盤のようにしっかり根を張るように」という豊作への願いを込めてタコを食べる習慣があるようです。
京都
京都では夏至の期間となる6月30日に、水無月という和菓子を食べる風習があります。
愛知
愛知県の一部地域ではいちじく田楽を食べる習慣があります。 夏至の日にいちじく田楽を食べる風習には、無病息災や不老長寿を願う気持ちが込められています。
静岡
静岡では冬瓜(とうがん)を食べる習慣があります。
福井
福井県の大野市周辺の地域では、「半夏生鯖」と呼ばれている丸焼き鯖を食べる風習があります。
香川
香川では収穫した小麦を使ってうどんを作り、農作業を手伝ってくれた方々に振る舞うという風習があります。
まとめ
夏至は一年で一番昼が長い日。太陽の光をたっぷり浴びられるこの機会に、普段より少しだけ昼間の長さを意識してみませんか?もし何か地域の夏至の風習があれば、この機会に体験してみるのも面白いかもしれませんね。
季節の移り変わりを感じながら、自然の恵みに感謝して毎日を大切に過ごしましょう。